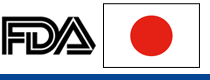ISO9000の概念
ISO9000は、ISO(国際標準化機構)で制定した品質経営システムに関する国際標準として、全世界、全業種、製品に適用されています。
ISO9000認証は、企業が運営している品質経営システムがISO9000シリーズ規格の要求事項に適合するよう規定され実行されていることを、国家が認める認証機関が保証する制度です。
ISO9000認証の必要性
開放された国際市場でのISO9000に対する要求のため
国家間産業標準の差による貿易障壁の克服
消費者の水準向上による品質の重要性の増大
市場での競争深化でサービスの質に対する重要性の拡大によりISO9000認証の獲得は必須
ISO9000認証効果
企業イメージの向上による売り上げの増大および輸出の障壁克服
グローバル化された市場で多くの取引先がISO認証を取引引き開始の前提として要求
企業内外部の信頼性増大
業務体系が整備されて公信力が高まり社員の自負心が鼓舞される
品質の革新と技術開発の基盤
品質安定のない品質革新は「砂上の楼閣」
徹底した文書化と記録管理による一人一人のノウハウと情報の資料化、資産化(企業のノウハウ蓄積)
責任と権限の明確化
体系化された社員教育プログラムの確保が可能
個別顧客からの重複審査の排除
製造物責任(PL)制度に対する最適な対応策
予防活動の最大化で失敗率減少(品質費用削減→利益増大)
予防費用
評価費用
失敗費用
削減
認証前 認証後
0% 20% 40% 60% 80% 100%
10% 10%
20% 20%
70% 70%
0% 0%
20% 20%
20% 20%
40% 40%
20% 20%
ISO認証
ISO9000認証に対する支援と恩恵
■ 現在、ISO認証を獲得された企業に対する支援策は次のとおりです。
政府調達時、認証獲得企業の製品に対する指名競争入札および随意契約が可能
KS表示許可審査時の工場審査免除(産業標準化法の施行規則 第16条および第22条)
兵役指定業者 推薦基準に含む
団体随意契約 物品配分基準上、恩恵基準40%適用
技術信用保証基金の技術優待 加算点付与
建設技術管理法に基づく加算点付与(第47条に基づく施工能力評価およびサービス業者のサービス能力評価時に加算点付与)
租税特例制限法に基づく技術費の税額控除(租税特例制限法 施行令<1998.5.16>第9条)
その他- 首都法による首都用資材基準に該当(認証獲得義務品目- 首都法第13条および第18条による首都用資材)
■ 現在の協議中にある政府追加支援事項は次のとおりです。
「租税減免規制法」施行令上、認証獲得企業に対する租税減免を現行の認証獲得費用(コンサルティング費用、審査費用など)に認証維持費用(事後管理費用)までが含まれるよう財政経済院に要請中
公共建設工事の事前入札資格審査時に認証獲得企業に付与加算点を上方修正するよう調達庁に要請(現行2点→5点、合計100点)
認証獲得企業に外国人産業研修生を優先的に配分するよう通商産業部、労働部に要請
技術信用保証基金の認証獲得企業に対する加算点の上方修正を推進(現行40点、合計100点)
その他、他法令による支援策を模索中
ISO9000推進手順
ISO9000認証コンサルティングプログラム
コンサルティング契約
予配診断
推進計画 樹立
推進担当者
管理者
全社員教育
品質システム樹立
品質マニュアル作成
品質手続き作成
その他標準文書確立
品質システム教育
品質システム実行
内部監査実施
経営検討実施
問題点是正処置
予備審査
文書審査
本審査
是正処置
認証取得
品質システムの樹立
実行
認証審査
最高経営者が設定した企業目的を達成する為の品質経営体系を確立
ISO14000の概念
ISO14000シリーズは、組織の全活動・業務を体系化し、最も効率的な管理システムを構築するため世界共通の基準として採用されました。企業が環境経営システム(EMS)を実行、維持、改善、保証することで、企業活動による環境への悪影響を最小限に抑え、エネルギーと資源の消費・再生を効率的に両立していることを客観的に証明する認証制度です。
ISO14000概念図
環境保護+汚染防止
環境影響評価
環境目標設定
履行計画樹立および実行
定期的な点検
是正処置
持続的な改善
環境経営体系(EMS)の紹介
従来の環境保全
公害防止活動
行政指導型
法規制遵守
排出規制中心の管理
担当の組織のみ対応
End-of-Pipe
法規遵守の事後的で消極的な単純測定活動が中心
➜
環境経営活動
自主判断
法規制以上の自主環境
基準設定および運営
排出源(根源)からの管理
全社的、能動的、予防的な体系化した活動
Pollution Prevention
企業の成長と競争力の拡大のための経営戦略的活動
導入の必要性
環境意識の高まりに伴う消費者ニーズへの対応と、環境配慮型製品への関心向上
企業の環境規制への適合状況を客観的に検証
国際市場における環境経営への対応要請
環境汚染に対する企業責任の拡大
ISO 14000
利害関係者の要求事項
生産製品の競争力強化
地域環境保護
企業イメージの改善
認証/登録の獲得
経営体制の実行・維持・改善
認証効果
■ 背景 環境汚染による世界的な環境への関心の高まりにより、欧米先進国と先導的企業が環境経営へと移行しています。ISO14000やISO 9000のような規格は一般化が進んでいます。
■ 環境部の<環境に親和的な企業>に指定される時の優待措置
大気・水質環境保全法による排出施設の設置許可申告
防止施設設置資金の融資優先適用(中小企業)
随時地図/点検の免除(汚染事故発生・陳謝時は実施)
定期地図/点検の免除
各種表彰時の優先適用
■ 現行の政府支援事項
認証獲得企業への税制優遇(コンサルティング費用、審査費用、事後管理費用を含む)
公共建設工事入札審査時の加算点付与
外国人産業研修生の優先配分
技術信用保証基金の加算点優遇
その他法令による支援策実施
■ 認証取得による効果と社内利益
企業イメージ改善
環境苦情・訴訟リスクの低減
法令違反リスクの低減
利害関係者との関係強化
廃棄物処理費用の削減
原材料・エネルギー使用量の削減
環境事故ゼロ化と費用削減
法規制への予測・対処能力向上
環境改善による自主的取り組み
環境効果と状態の改善
環境影響の継続的管理
市場競争力の向上
ISO9000との比較
区分 ISO9000 ISO14000 管理 改善目標 無欠点 無欠点、非排出、無汚染 原則 経済性 経済性、環境親和性 評価 監査 会計監査 会計監査、環境管理システム監査、製品寿命周期 監査、放出最小化監査、政策順応監査など 評価者 顧客 顧客、株主、従業員、民間団体 機能 生産 高品質、生産性増加 高品質、廃棄物減少/資源節約/梱包材など生態系に 関心、エネルギー費用削減 研究開発 製品に集中 原料から最終廃棄とリサイクルまで考慮 マーケティング 市場占有率の増加 無欠点、非排出、無汚染
ISO14000推進手続き
ISO14000に関する一般教育 EMSの内容への為の教育 初期環境性の検討 業務の方向性決定 社内実務者教育訓練 EMS実務者教育 EMS専門教育 内部監査養成教育 環境影響評価 1.環境性評価初の方法設定 2.環境性評価の実施 3.評価内容の品質 4.実施可能性の最終確認 5.環境経営プログラムの設定 環境文書化作業 必須環境文書の制定作業 環境改善プログラム 環境影響評価の結果を土 台に短期/中期/長期計画 の樹立 内部監視 現地監視 認証検査 予備調査 文書審査 本審査 是正処置 認証取得
ISO22000(食品安全経営システム)とは?
2005年3月、全世界14カ国がISO傘下の技術分科委員会(Working Group 8)に参加し、国際的に認知された食品安全に対する経営システムを採用しています。この技術分科委員会には、CODEX(国際食品規格委員会)、GFSI(Global Food Safety Initiative:国際食品安全協会)、CIAA(European Food Industry Organization:ヨーロッパ食品産業協会)等の組織が参加しています。
規格の適用範囲は飼料および食品供給網全体を包含しており、食品安全経営システム(ISO22000)は審査規格としてISO 9001:2000とHACCPシステムの内容を統合しています。
導入の必要性
食品安全の確保は食品に起因する事故の拡大を防止する上で必要不可欠です。消費者の食品安全性に対する要求が高まっているため、食品の製造および管理に関する標準化された経営システムの導入が進んでいます。
品質経営システム(ISO 9001)が食品業界に導入されましたが、食品の機能と品質中心に焦点を当てる傾向があり、食品安全に関して十分な対応が困難でした。
その結果、企業によってはCODEX(国際食品規格委員会)で推奨されるHACCPシステムを別途導入し、食品衛生の課題解決を目指すことになりました。しかし、これにより二種類のシステムを同時に運営する負担が増加しました。
また、各国で独自の食品規格およびシステム管理が行われてきましたが、国際間の食品取引が増加し、このような状況が消費者に混乱をもたらしていました。
規格の要求事項
この規格の基本的な要求事項は以下のとおりです:
食品安全危害要素の把握および危険分析
食品安全管理、検証および妥当性の確認
食品安全経営システム要素
GAP(Good Agricultural Practice:適正農業規範)、GMP(Good Manufacturing Practice:適正製造規範)
GDP(Good Distribution Practice:適正物流規範)
規格の構造はISO9001とISO14001規格の要求事項と類似していることから、リスクに基づいた統合的な経営システムの構築が可能です。
進行状況(2024年現在)
ISO 22000は2005年の初版発行以降、以下のような進展を遂げています:
2018年に大幅な改訂が行われ、ISO 22000:2018として発行
主な改訂ポイント:
ハイレベルストラクチャー(HLS)の採用による他のマネジメントシステム規格との整合性向上
リスクに基づく考え方の強化
プロセスアプローチの明確化
PDCAサイクルの二重構造の概念導入
現在、ISO 22000:2018は世界中で広く採用されており、食品安全マネジメントシステムの国際標準として定着しています。組織は2021年6月までに2018年版への移行を完了しており、新規認証は全て2018年版で行われています。
また、GFSIによる承認も得られ、食品安全の国際的な枠組みの重要な部分として機能しています。ISO 22000ファミリー規格(ISO/TS 22002シリーズなど)も継続的に開発・更新され、より包括的な食品安全管理の実現に貢献しています。
食品安全経営システムの構造
ISO-22000 食品安全経営システム
検証
(経営検討)
保安
移行
要求事項
入力要素
プロセス
製品
顧客
危害要素把握
危害要素分析
重点管理
要求事項
入力要素
プロセス
製品
顧客
一般管理